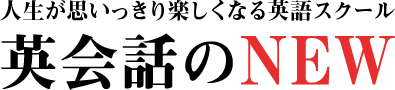◆◇◆ 目 次 ◆◇◆
◆一般動詞について◆
◆副詞の位置について◆
◆過去形と過去進行形の違い◆
◆be going to~◆
◆第6回講義(助動詞)◆
◆第6回講義&zoom (助動詞 canとbe able to)◆
◆第9回前置詞(at bus stop)◆
◆第9回前置詞(at night)◆
◆現在完了形◆
◆テキストP.237 5(6)◆
◆副詞の位置◆
◆take part inについて◆
◆On her way backについて◆
◆The Bluenose P2-L4◆
◆テキストP403
◆名詞の所有格について◆
◆数詞の品詞について◆
◆English is……all over the worldについて◆
◆◇◆ Q A ◆◇◆
【English is……all over the worldについて】
■質問■
English is……all over the world
all over the world の品詞等について質問です。
①(all over the world)直前のspoken を修飾しているから
副詞句でよろしいでしょうか?
② overの品詞は、the worldの前にあるから前置詞、
allは over the world 副詞句を修飾しているから
副詞ですか?それとも、over 形容詞を
修飾しているから副詞ですか?
ご教示頂きたくお願いします。
■解説■
ご質問ありがとうございます!
結論から先にお伝えすると、
①の回答は「前置詞のかたまり」です!
※他の参考書ではこの前置詞のかたまりを副詞句や
形容詞句として捉えることがありますが、
アドバンスでは第2回アドバンス講義でお伝えした通り、
SVOCどれにもならない塊として考えます。
②overとallの品詞について
overはご理解いただいている通り後ろに
名詞がきている=前置詞でOKです^^
allはこの場合、副詞として捉えます!
※アドバンスでは代名詞/形容詞としての用法しか
お伝えしていませんが副詞の役割もあります。
副詞は「名詞以外は全て修飾する」
というルールがあるのですが、
前置詞のかたまりも修飾することができます^^
今回はover the worldという前置詞のかたまりを
allが修飾しているという形ですね!
基本的な質問とおっしゃってましたが、
・問題以外の部分もしっかり品詞を見ようと意識できていること
・今まで学習したことを踏まえてまず自分で考えてみようとしていること
・そして分からないことを言語化して質問できていること
ができているのでめちゃくちゃ良い学習習慣が身についてると思います^^
自信を持って文法が出来る!!
というのはなかなか難しいと思いますが、
着実にアドバンスでつけていただきたい知識と姿勢を
身につけていただけてるので順調です!
後半戦もどうぞ宜しくお願いいたします
【数詞の品詞について】
■質問■
数詞の品詞についてのご質問です。
The Grand Canyonのパラグラフ1の3行目にある
”It is 446 kilometers long “とパラグラフ3の1〜2行目
にある”the canyon for thousands of years.”
この2つの違いが飲み込めません。
自分は446とthousandsの両方を名詞と答えました。
前者の446が形容詞という理由は、テキスト等を見て
kilometers という名詞を修飾しているからだと
思ったのですが、”for thousands”も後ろの
of years(名詞の塊)を修飾していると思うので
同じように感じています。
thousand の前に前置詞があるから名詞になるのでしょうか。
根本的なところが分かっていない気がしています。
基本的な部分で申し訳ありません。
ご教示くださいますようお願いいたします。
■解説
いくつか前提の整理が必要なのでそこから解説しますね^^
1.数詞について
寺子屋、アドバンスを通して品詞をいくつもご紹介してきましたが、
数詞はこれらの品詞の分類とは少し異なります^^
前回の講義でご紹介した通り、形容詞は
・数量形容詞
・性状形容詞
に分類されます。
数詞はこの「数量形容詞」の一部に分類されます^^
2.数を表す単語の品詞
thousandを調べていただいたら分かると思いますが、
数を表す単語は「名詞」と「形容詞」の2つの品詞を持ちます^^
The Grand Canyonを例にとってみても
446 kilometers の時は形容詞
for thousands of yearsの時は名詞
のように文章によってどちらも使います!
3.名詞を修飾する品詞
※第7回寺子屋Zoomもしくは第1回アドバンス参照
ここは復習になりますが、名詞を修飾するのは【形容詞】だけであり、
副詞や動詞、前置詞の塊が名詞を修飾することはないです^^
※めちゃくちゃ稀に副詞が名詞を修飾しますが、
かなり特例なので気にしなくてOKです。
ここまでが前提です。
4.カッコ
それを踏まえた上で今回の
in and around the canyon for thousands of years
を見ていきます^^
これに限らず全ての長文を見る時は、
1.まずカッコ
↓
2.SVOC
↓
3.品詞
の順番で見ていくことを徹底してくださいね^^
で、カッコをすると
( in and around the canyon )
( for thousands )
( of years )
となり全て前置詞の塊となりますね^^
※前置詞の後ろには名詞or名詞の塊が来ます
(第2回アドバンスのルール⑥参照)
3で先述した通り、
前置詞の塊が名詞を修飾することはないのと、
形容詞は名詞のみを修飾するので前置詞の塊を修飾することはありません。
それに対して、
it is 446 kilometers. (longは今回の解説では不要なので端折ります。)
をカッコすると、
it is ( 446 kilometers )となります。
カッコの中に関連のない名詞が2つ並ぶことはないので、
446は形容詞で後ろのkilometersを修飾していると考えます。
※ The Bluenoseの boat raceは名詞が2つ並んでますが、
2語でボートレースという意味なので別
また、kilometersを見ると、 複数形のsがついてますよね。
これは446という複数を表す形容詞で修飾されているからです^^
以上から、
・thousandsは名詞
・446は形容詞
となります。
その他
これはテクニックに近い観点ですが、
英単語の後ろにs(es)が付く品詞は2つしかありません。
・動詞の三単現
・名詞の複数形
この2つです^^
thousandsは元々thousandにsが付いた形なので
形容詞ではなく名詞になります!
※第4回アドバンス最後の練習問題参照
長い解説になりましたが、非常に大事なところなので
是非ご一読ください^^
【名詞の所有格について】
■質問■
〈名詞の所有格についての質問〉
’sの付け方について知りたい
■解説■
所有格についてははあまり聞かれることが
ないですがとても大事な箇所なので、
前提の部分から解説することにします^^
●所有格の種類
所有格は後ろの名詞の所有者を表す表現ですが、
大きく分けて下記の2種類があります。
①代名詞の所有格
②名詞の所有格
このうち①はテキストP.150に記載されており寺子屋でも
繰り返し出てきたところなので解説は割愛します。
● ’sとof所有格
②の名詞の所有格は名詞の後ろに’sを付ける形ですが、
これと同等の意味で ofも使われます!
どちらもほぼ同じ意味なのですが使われる場面が違っていて、
・’s = 人間や動物のみ
・of +名詞 = 無生物(生き物以外)の時
となっています。
例えば「家の屋根」と言いたい時、
家は生き物ではないので、
the house’s roof
ではなく
the roof of the house
と表現します。
ただし、「地名」や「天体/施設」、「時間/距離」などの場合は、
無生物ですが ’s の形を取ります!
ここまでが前提です。
これを踏まえた上で ’sの付け方(’がない時など)を教えて欲しい
というのが今回の質問の内容でしたので、
ここからが本題です笑
●’sの付け方
①単数名詞の所有格
→名詞の後ろに ‘sを付ける
Ex) Mike’s house, Tom’s birthdayなど
②複数名詞の所有格
これは2パターンに分かれます!
②-1 『-sで終わる名詞』
→ (‘) だけを付ける
Ex) ladies’ dress, birds’ nest など
②-2『-s以外で終わる複数名詞』
→ ’sを付ける
Ex) children’s toys など
【注】 sister’sとsisters’
所有格でややこしいのがこのパターンだと
思うのですが、
これは上の原則に従えば簡単です^^
・sister’s
はsisterという単数名詞にくっついてるので①が該当し、
「姉の」という意味になります。
・sisters’
はsistersという複数名詞にくっついてるので、
②-1が該当し「姉たちの」という意味になります。
③固有名詞の場合
固有名詞の場合でも①②の原則に従うのですが、
・古典の人名
・’sだと発音しにくい場合
についてはsを省いて (‘)だけを付けることがあります!
一旦、私が把握している質問の内容は上記になりますが、
さらに解説すべきところがあればご指摘ください!
【テキストP403】
■質問1■
①テキストP403 5の(3)
I met Mr.Tanaka, who taught me English at high school.
この文の関係代名詞の前に入るカンマについて
知りたいです。加えて、解答の訳が、
私は田中先生に会いました…と、前の文、後ろの文と
順番そのままに訳されています。
これは、カンマがあるからですか?
■解説1■
●【前提】関係代名詞の前にあるカンマ
今回の課題のように関係代名詞の前に
カンマがつくことがあります。
I met Mr.Tanaka, who taught me English at high school.
これらは、関係代名詞の節が下記のどちらの
用法で使われるかで決まります。
・カンマなし→制限用法
・カンマあり→非制限用法
※制限という言い方をするとややこしいので、
「先行詞を関係代名詞の節で限定(特定)する
必要があるかどうか」と考えてください。
・特定する必要がある→制限用法
・特定する必要がない→非制限用法
今回の文章の場合、whichの前にカンマがついているので、
先行詞を限定する必要のない非制限用法となりますよね^^
●制限用法と非制限用法を決めるもの
まず、どちらの用法になるか(カンマを付けるか付けないか)
で大事なのは、関係代名詞の節ではなく、
修飾される〈先行詞〉です。
▼制限(限定)する必要がある場合→制限用法
The person who wrote this essay is one of my friends.
この文章の場合、the personだけでは「どこの誰か」
を特定することができず、who wrote this essayという
説明が加わって初めて特定=限定することができます^^
▼制限(限定)する必要がない場合→非制限用法
The earth, which moves around the sun, is called a planet.
それに対して、The earthは1つしかないので特定=限定する
必要がないので、カンマをつけて非制限用法にします。
この他にも、
①先行詞が固有名詞の場合
②先行詞が前の文脈から特定できる場合
③先行詞が同一の種類すべてを指している場合
は非制限用法を使います^^
今回のP2-L3は①に該当しますね!
ちなみに、
Mr.Tanaka who taught me 〜.
にするとwho taught me 〜.
で初めて特定されることから
「(他にも田中という名前の人がいる中で)
私に英語を教えてくれた田中先生」
というニュアンスになります。
●非制限用法の役割
制限用法では先行詞を特定する役割があるので、
先行詞を関係代名詞の節が修飾し限定する
という関係が成り立ちますが、
非制限用法の場合、この関係は薄くなります。
つまり、「”私たちに英語を教えてくれた” 田中先生」
と限定する必要がないので、
補足的に「(ちなみに)私たちに英語を教えてくれた」
くらいの感覚になります。
なので、今回の日本語訳も分けられている
のではと思います^^�
■質問2■
②テキストP403
6の(1)
These are the pictures taken by my brother on the trip.の、
tripにonがつく感覚が分かりません
onのコアは、時、場所を表すだと理解していますが。
■解説2■
こちらは元の意味の違いと、
ビジネスの場面での違いがあるので分けて解説しますね!
●speakとtalkの意味
まず、「話す」という意味の英語は主に
speak, talk, say, tellがありますが、
・話す「行為」に注目=speak, talk
・話す「内容」に注目=say, tell
に分けられます^^
speakとtalkはどちらも「行為」に注目するグループに
分類されますが、ここからさらに細分化されます。
①speak=「一方的に話す」
speakは話し相手や内容に注目をせず「言葉を発している」
ということに注目をしています。
speakerは演説などで一方的に喋っていますがあのイメージですね^^
②talk=「会話する」
それに対してtalkは相手との会話をする場面で使われます!
自分だけでなく相手も話しているイメージですね!
今回の場合、電話でお互いが話していることになるので、
speakではなくtalkになります。
●speakはフォーマル
ビジネスの場面になると上記から派生して、
speak=フォーマル
talk=カジュアル
という使い分けがされています^^
例えば「お話しても良いですか?」と言いたい時、
speak, talkどちらも使えますが、下記のような違いがあります。
・May I speak to you?
こちらは仕事の場面で重要なことを一方的に伝える時に使われます。
・May I talk to you?
こちらは一方的ではなく対話をしたいというイメージですね!
それぞれのシチュエーションに応じて使い分けてみてください^^
■質問3■
③テキストP403
7の(2)
The girl who is talking on the phone is my sister. は、
speaking ではだめなのですか?電話に出た時だけ、
I am speaking.とかって使いますか?
■解説3■
これはめちゃくちゃいい質問ですね!
onは「接触」がコアの意味ですが、ここから派生して
「計画に沿って」というニュアンスがあります!
※計画に接触している=計画通りという感じですね
例えば、
on timeは「時間通り」
on scheduleは「計画通り」
という意味になりますよね^^
on the tripは事前に立てた計画通りに
旅行をしているので、onが使われています!
【The Bluenose P2-L4】
■質問■
The Bluenose
P2-L4 From then の品詞について
先生の解答では、thenには名になっています。
辞書には、名詞ではなく副詞、
ちょっとだけ形容詞と出ています。
副詞の中に、「前置詞の目的語に用いて;名詞的に」
とありました。
この意味での名詞で、通常、thenは副詞と
考えていてもよいですか?
P4-L1 it hit a coral reef の品詞ですが、
coralは、natural やsocial みたいなalで終わる
形容詞かと思いました。
辞書には、名詞、ちょっとだけ
形容詞と出ています。
これは、一般的にcoral reef というひとくくりの
名詞になっているから名、名ということでしょうか?
■解説■
ご質問ありがとうございます!
私は「ジーニアス英和辞典 第3版」を使用していまして、
そちらを元に解説をさせていただきますが、
ご使用になられている辞書とは相違があるかもしれません。
ご了承ください。
●P2-L4 「from then」について
thenが1語のみで使われる場合はご理解いただいている通り
副詞として機能しています^^
今回は前の単語がfrom (前置詞)になっていて、
今までのルールに沿えば「前置詞の後ろは名詞(かたまり)」
となるのでここに副詞が来ることはありません。
なのでこの場合、thenは名詞として機能することになります!
これで、前置詞+名詞のいつも通りのルールとなります。
ちなみに、from以外だと
before, till, until, sinceなどが使われます^^
●a coral reefについて
こちらはジーニアスだと名詞のみとなっています。
coral reefでまとめて「サンゴ礁」という意味では
あるのですが、一つ一つの品詞に注目するという点で
どちらも名詞として記載をしています^^
冠 名詞 名詞となるので少し違和感を覚える部分かと
思いますが、(会場で受講いただいた時も
この質問いただいてましたよね)
あくまで coral reefという1つの意味のものを
敢えて2つに分けた場合、便宜上 名詞が続いて
しまっているとお考えいただければと思います!
以上、宜しくお願い致しますm(_ _)m
【On her way backについて】
■質問■
On her way backについて、質問があります。
backの品詞は副詞、文法の解説にbackが
後ろからOn her wayを修飾となっているのですが、
副詞は名詞以外を修飾するルールから
外れているのように見えるのですが。
自身の解答としましては、wayが名詞で、
名詞を修飾するbackは形容詞としたのですが。
何故副詞になるのでしょうか?
■解説■
ご質問ありがとうございます^^
少し考え方を修正した方が良いところが
ありますので前置きが長くなりますが、
解説していきますね!
前提① 名詞の仲間※第2回アドバンス中盤参照
名詞の仲間になれるのは、
・名詞
・代名詞
・名詞の塊
・不定詞の名詞用法
・動名詞
・名詞節
これらは文章の中でSOCのいずれかになります!
前提② SVOCどれにもなれないもの
※アドバンス 第2回終盤参照
・副詞(句/節)
・前置詞の塊
上記の前提①②を踏まえた上で、
今回議題に上がっている部分を見てみると、
on her wayは名詞の塊ではなく”前置詞の塊”
になるので、名詞ではありません^^
ここまでが前提です!(長くてすいません笑)
●on her way backの考え方
まずいつものルール通り
カッコをすると、
( on her way ) back
となりますよね!
ちなみにこの on her wayは場所を表す副詞句
として機能しています。
副詞はご理解いただいている通り、
“名詞以外を修飾する”ので、副詞が副詞を
修飾することもあります^^
※ very wellとかもそうですね!
まとめると、
on her way という場所を表す副詞句を
back(副詞)が修飾をして「方向」を
加えているという考え方になります!
on her way(彼女の道)
+
back(戻ってくる)
つまり、彼女の帰り道となります^^
【補足】名詞を修飾するものとその位置
※第1回アドバンス参照
名詞を修飾するのは「形容詞」ですよね!
そして名詞を修飾する形容詞は名詞の
直前に置かれます^^
※スライド22 ルール④参照
なので、way(名詞)をback(形容詞)が
修飾するのであれば、on her back wayの
順番にならないと成立しないです。
ちなみに、
形容詞が名詞を”後ろから”修飾する
特例はあるのですが、それは今回の長文課題で
出てるので探してみてください^^
長くなりましたが非常に大事なところですので
ゆっくり噛み砕いていってください!
以上、宜しくお願い致しますm(_ _)m
【take part inについて】
■質問■
文中に出てくるtake part inについて。
品詞を書くときのイディオムについては、
前回のbe going to のように、まとめて動詞
とすればよいのでしょうか?
もし、これがイディオムだと知らなかった場合は、
推測で意味がとれるようになりますか??
■解説■
●イディオムの対応について
今回のThe Bluenoseではtake part inという
イディオム(熟語)が使われていますが、
流れとしては下記をオススメします^^
1.まずルール通りのカッコ
take = V
part = O
in +名詞 =前置詞の塊
というようにSVOCとカッコを分ける
↓
2.辞書で調べる
それだと意味が通らないので辞書を引いて、
take part in 〜で「〜に参加する」
という意味を空欄に記入し、
カッコなどはそのまま置いておく
文章を理解するという意味では
take part inでVとした方が良いのですが、
“現時点では”カッコを分けた方が
文法力/リーディング力が付きます^^
こうお伝えする理由は2つあって、
①イディオムを考えると日本語訳で捉えてしまう
リーディングに強くなるには
「英語を英語で捉えること」
が(最初は難しいですが)非常に大事で、
言い換えると、英語で捉える=日本語で考えるのを
辞めるということなんですよね。
となるとイディオムを日本語で覚えてしまってると
日本語訳が入るのでこの思考が抜けにくくなって
しまいますm(_ _)m
②カッコのルールを徹底的に叩き込むため
第3回までに品詞→かたまり→SVOCとルールに沿って
少しずつ広げていって文章の骨組みを解説しましたが、
このルールをどんな文章が来ても大丈夫なくらい
徹底的に頭に入れていただきたいという思ってます^^
アドバンス中盤で
「take part in でまとめてVとしても大丈夫ですよ^^」
とお伝えするタイミングがあるので
一旦は上記でご対応いただければと思いますm(_ _)m
●「これがイディオムだと知らなかった場合は、
推測で意味がとれるようになりますか?」について
いろんな文章を読んでいくと
「どう考えても意味通らない」
↓
「ということはイディオムかも」
という推測ができるようにはなりますが、
意味まで掴むのはかなり難しいかなと。
なので、イディオムはアドバンス終盤で単語帳などを
買って覚えるのが良いかと思います^^
長くなりましたが、
以上宜しくお願い致しますm(_ _)m
【副詞の位置】
■質問■
副詞の位置に関する質問です。
文中、一般動詞の場合は一般動詞の直後、
ただし目的語がある場合は一般動詞の直前と
教わりました。
テキスト170の1①には、動詞が目的語をとるときは
目的語のあとに置く。
テキスト171のチェック頻度を表す副詞
①一般動詞の文では一般動詞の前に置く。
■解説■
●副詞の位置が曖昧な理由
副詞の位置ってややこしいですよね。。。
多くの人が最後まで悩む品詞が副詞です!
理由からお伝えすると動詞を修飾する副詞は
「ここに置かなければならない」
という明確なルールがなく、
「だいたいこの辺なことが多い」
という曖昧な品詞だからです^^
第2回の「動詞を修飾する副詞の位置」で、
文頭、文中、文末と書いたのはそのためです。
例えばテキストP.170の
My father read the letter carefully.
は文末から動詞を修飾してますが、
My father carefully read the letter.
としても文法上間違いではありません!
ただ、この文章だと上の方が頻繁に
使われるイメージがあります。
●副詞を掴むために
で、なぜ副詞の位置が曖昧かというと
ルールよりも「リズム」で決まることが
多いからです。
先ほどの文章も、
My father read the letter carefully.
の方が自然な流れで読めるから文末に
置くといった形ですね。
リズムってなに?となると思うのですが、
この副詞の位置を感覚で掴むためには
「音読」がとにかく大事です。
これから出てくる長文課題をとにかく
音読してリズムを徐々に掴んでいってください^^
●アドバンスでの対応
副詞はずーっと時間をかけてマスター
していくもので、すぐに完全に理解するのは
難しいです。。。
そのためにアドバンスでは、
・名詞/前置詞の塊を理解する
・混同されがちな形容詞を完璧にマスターする
そして上記以外=副詞
という順番で徐々に副詞の輪郭を掴むという
流れを汲んでます。
なかなかに強敵な副詞ですがマスターすれば
強い味方になりますので、
一つ一つ理解を深めていきましょう^^
引き続き宜しくお願い致します。
【テキストP.237 5(6)】
■質問■
テキストP.237 5(6)の回答に「教えてくれる」とあったのですが、
この文のどこから「くれる(恩義)」の意味が出せるのでしょうか?
こう言ったニュアンスを出す部分、会議中は単語のスピードや
強弱で気持ちを乗せていますが、文章にも乗せられるのであれば、
ぜひ知りたいです。
■解説■
まずテキストP.237(解説P.529)にある日本語訳で
「スズキ先生は私たちに英語を教えて”くれる”」
と表現されていることについてですが、
これはこの参考書の意訳ですね!笑
もちろん、こちらも合ってるのですがこの文章だけでは
「教えている」なのか「教えてくれる」なのかまでは分かりません。
●「〜してくれる」のニュアンス
かと言って「〜してくれる」という表現が英語には
ない訳ではありません。
参考までにいくつかご紹介しておきますね^^
・be willing to 原形
割とよく使われる表現ですが、
「よろこんで〜する」というニュアンスになりますね!
が、今回の「〜してくれる」とは少しだけ逸れるかもですね。。。
・kindly
これは第2回、第3回で扱った「動詞を修飾する副詞」でして、
「親切にも」というニュアンスが加わるので結構使えます^^
この副詞の位置はノートに書いていただいた通りですので、
Mr.Suzuki kindly teaches us English.となります^^
・be kind enough to 原形
少し難易度を上げるとこの表現を使うこともできます!
enough to do 「〜するのに充分」という表現の発展系ですね!
Mr.Suzuki is kind enough to teach us English.
是非参考にしてみてください^^
以上、宜しくお願い致します。
【現在完了形】
① I have started playing tennis.はどの用法か
② 継続を示唆する際の過去形と完了形について
③ 完了形の考え方
■質問■
■現在完了形(講義内容についての質問ではありません。)
・startについて
The rainy season has started. は「梅雨が始まった」で「完了」
だと思うのですが、I have started playing tennis. は「継続」
でしょうか?
“start”が「継続」しているという状況がイメージし難く
「続いている」のは”start”ではなく、その後の動名詞の方では?
と思ったりもします。「startに継続ってあるの?」って感じです。
(他の用法に分類されますか?ここでは一旦、
現在完了形の継続用法であるとして話をすすめます。)
もちろん過去形だと、ある過去の時点で「始めた」こと
しか伝えられず、いまも続けているかが不明になる感覚はわかります。
なので「今も続いている」感を出すために現在完了形を使う
という論法はわかるのですが、どうしても”start”という動作動詞
「始める」が「続いている」という感覚が掴めません。
これは、過去形では「いまも続いている・やっている」という
意味を伝えることができないから現在完了形になる、
と割り切った方がいいですか?
そもそも、動作動詞で「継続」の内容を表すなら、
現在完了進行形の方がメジャーでしょうか。
つまり、動作動詞の現在完了形は主に「完了」であって「継続」
は稀でしょうか?
(動作動詞で完了していること
→現在完了形/継続していること→現在完了進行形)
ただし、“start”は一瞬の動作しか表現できないので進行形
(現在完了進行形にすること)はできずに、結果的に
現在完了形になる。この考え方は合っていますでしょうか?
自分なりに調べてみたのですが、上記内容が頭の中を
グルグルしている状況です。
宜しくお願い致します。
■解説■
ご質問ありがとうございます!
質問の項目としては
① I have started playing tennis.はどの用法か
② 継続を示唆する際の過去形と完了形について
③ 完了形の考え方
ですね!順に解説します^^
①結論からお伝えすると I have started playing tennis.は
「完了」の用法ですね^^
英語の動詞にはいくつか種類がありますが、
start, finish, die などは「瞬間動詞」として分類されていて、
ご理解いただいている通りstartであれば「始まる/始める」
は一瞬で終わるため、継続の意味を持たせることはできません。
なので現在完了の継続の意味では使えずに完了の意味になります^^
② 継続を示唆する際の過去形と完了形について
こちらについては、なぜ完了形をわざわざ使ったのかが
ポイントかなと思っていてただ単に過去の事実を伝えたいのであれば、
I started playing tennis four years ago.などで伝えられるのに、
わざわざ完了形にしているということは現在とのつながりを
表したいということになりますね。
ここからはニュアンスの話ですが、過去にテニスを始めて
辞めたのであれば過去形で表せばよいところを
現在完了にしている→過去にテニスを始めたということが
現在にもつながっている(影響を与えている)→つまり辞めていない
という感覚になるのかなと。。。
この1文だけで判断するのは到底難しいですが
ニュアンスとしてはそんな印象を受けますね^^
③完了形の考え方
現在完了というくらいですから完了の意味で使われる割合は
かなり多いと思います。
ただ、継続も同じくらいよく使われていてその際は
for 〜/ since 〜と共に使われてこの完了形が「継続」の意味ですよ!
と読み手にもしっかり伝わる形で書かれてますね^^
ただし、“start”は一瞬の動作しか表現できないので進行形
(現在完了進行形にすること)はできずに、
結果的に現在完了形になる。
→ここはその考えで概ね大丈夫かと思います^^
文章だけだと伝わりにくい部分もあるかと思いますが、
以上、宜しくお願い致します。
【第9回前置詞(at night)】
■質問■
■第9回前置詞
・at night
atは「点」なのになぜnightの前置詞になり得るのでしょうか。
(at midnightはジャスト12時を指すので
atになることはわかります。日本人がイメージする「深夜」
という幅がある時間帯はin the middle of the nightになって、
in が使われるのも納得です。)
一方でnight「夜」には「時間的幅」を感じます。
なのにatなのは何故だろうかと色々調べると、
「夜は寝ているので時間的幅を感じないから」
という意見がありました。
納得できるような、できないような(笑)
先生はどのように思われますか?
■解説■
ご質問ありがとうございます!
めちゃくちゃ鋭いご質問ですね。
●時を表すinが持つ意味
inを使った時の表現として
in the morning
in the afternoon
in the evening
などが浮かびますよね^^
ここが大事なポイントなのですが、inが時間を表す時は
「時間的に幅があって且つ時が流れている」
という意味が込められています。
例えば、 I had a meeting in the morning.
であれば会議は一瞬ではなく一定時間
行われるものですから、
「午前10時〜11時までの間に会議があった」
のように、時間的な幅と1時間の時の
流れがありますよね^^
この場合に in を使うわけです。
●時を表すatが持つ意味
それに対してatは時の1点を表すのでat noonとか
at 10:00などピンポイントのイメージですよね!
で、これを言い換えると「時が流れていない」
という言い方ができるんですよね。
at noonであれば正午という時の一瞬を
表してはいますが、そこに時の流れは
含まれていないんです。
これが前提で、at nightは夜ですが夜の時間帯は
日中と異なり人々が眠る時間つまり活動がない
時間なんですよね。
なので「ベッドに入ってから起きるまで」は
時の流れがないのでinではなくatを使うんです^^
ただし、 in the nightという表現ももちろん可能で
この場合は時間の流れが発生している時に使います。
慣用句で、like a thief in the night (こっそりと)
という表現がありますが、これはまさに泥棒が
深夜に”活動している”イメージですね!
以上、宜しくお願い致します。
【第9回前置詞(at bus stop)】
■質問■
■第9回前置詞
・at bus stop
場所を表す前置詞のatの例文でat bus stop
とありましたが、busが無冠詞なのは何故でしょうか。
例えばby busはbusを物体と捉えるのではなく、
機能に着目して無冠詞になるのはしっくりきます。
しかしat bus stopは物体としてのbusであり、
冠詞が必要な気がしました。
と、ここまで書きながら思ったのですが、
by busと同じように手段を伝える表現としての
take a (the) bus には何故冠詞が付くのでしょう。
take a (the) busの場合はbusを機能や手段と捉えず、
takeの目的語として物体のbus
(takeするのだから、物体である必要がある)
ということでしょうか?
■解説■
すいません。。。
シンプルに冠詞入れ忘れてます。。
正しくは at the bus stopですね!
【第6回講義&zoom (助動詞 canとbe able to)】
■質問■
canとbe able toについてお伺いします。
「明日野球の練習これる?」みたいな、能力とは関係ない意味での「できるかどうか」を聞くときはbe able toですか?つまり、一時的な能力となるのでしょうか?
(「来て」という依頼の気持ちはなく、単に「来れるかどうか」を聞いている文章です。)
状況的にとかスケジュール的に参加できるかどうかは「備わった能力」ではないと思うのですが、「一時的な能力」でもない気がしています。
未来のことなのでcanやbe able toにとらわれず、willやbe going toを使えばよいのかもですが、「そもそも予定しているか」を聞きたい訳ではなく「来れるかどうか」的なニュアンスを聞きたいときはどう表現すればよいかな?と思いました。
宜しくお願い致します。
■解説■
確かに、
can = 身に備わった能力
be able to = 一時的な能力
という違いはありますが、これが明確になるのは過去形ですね、、、
過去形の場合は明確に分けた方が良いです!
が、現在形においては、be able toは堅いのでコアの意味に捉われずcanを使う方が無難です^^
「明日来れる?」と「明日来ることできる?」の違いみたいな感じですね!
willやhaveなど他の助動詞が絡む場合は当然 canは使えないので、be able to になるので、
・過去形の場合
・他の助動詞が絡む場合
以外はcanで大丈夫かと思います^^
【第6回講義(助動詞)】
■質問■
could とwould についてお伺いします。
例えば会社の同僚に資料の確認をお願いしたいとき、
couldとwouldとではどちらの方がよいでしょうか。
Could you check the document?
Would you check the document?
could だとcanの「可能」または「依頼」を過去形にすることで、
距離感を出して丁寧な表現へと押し上げている感じで、
would はwillという「意思」があるかどうかを、過去形にすることで
丁寧に聞いている、って感じがあるのですが、あっていますでしょうか。
wouldは、いくら過去形にすることによって丁寧な表現にしていても、
「そういう意思があるかどうか」っていう聞き方になり、
少し圧を感じるので、人に頼むときはcould を使った方がよいのかな?
と思うのですが、この感覚あっていますか?
■解説■
●英語の過去形
寺子屋の第6回講義でお伝えした通り、英語の過去形は「遠さの表現」です!
そして遠さは3種類あって
・時間的な遠さ(過去形)
・精神的な遠さ(丁寧表現)
・現実からの遠さ(仮定法)
となります^^
このうち、
Could you〜やWould you〜?は元々 Can you〜?とWill you〜?
だったものを過去形にすることで、精神的な距離を開けて遠慮がちに
聞いているニュアンスが加わります!
で、どちらを使えばいいか問題ですが、�Couldの元の形はCanで、
canのコアは「可能」Wouldの元の形はWillで、willのコアは「意志」
これは疑問文になってもcouldやwouldになっても変わりません。
なので、
Could youは相手に可能か(する能力があるか)を聞く時
Would youは(能力があるのはわかった上で)やる意思があるか
を聞いてる感じですね!
相手に能力がある(時間的余裕がある)上で、
意向をお伺いするwould you〜?の方がより丁寧な表現だと思われます^^
ただ、今回のご質問のように同僚の方であればどちらでもOKです!
【be going to~】
■質問■
![]() 第5回講義(未来形)
第5回講義(未来形)
③近い将来「~しようとしている」
についてなのですが、現在進行形(be doing~)で
表す近い将来のことと同じ感覚でしょうか?
別物だとしたら、使い分けはどういった
感覚でするとよいでしょうか?
■解説■
ご理解いただいてる通り、
be動詞+現在分詞(進行形の形)で近い未来を表すことができます^^
この場合、be going to〜と同じように思えるのですが、
be動詞+現在分詞の方が
「より確定的な未来/強い意志」が含まれてます!
【過去形と過去進行形の違い】
■質問■
■第四回講義
・過去形と過去進行形の違いについて過去形のときの
We play baseball last Fridayのlast Fridayは時間的幅が広く、
過去進行形のWe were playing baseball when you visited meの
when節はピンポイントとのことですが、過去進行形は「継続中」
の動作とのことでした。
私の中で「ピンポイント」と「継続中」というのは相反する感じがし、
継続中のことは広い時間内で行われているのでは?と感じたのですが、
過去形と過去進行形の使い分けは、過去形は
「過去の広い時間内(last Friday)における、その時の動作(played)」
を伝えるときに使い、過去進行形は
「ピンポイントの点(when節)における、継続中の動作(were playing)」
を伝えるときに使う、という解釈でよいでしょうか?
■解説■
こちらは概ねご理解いただいてる通りですが、
「ピンポイント」と「継続中」は切り分けて理解する必要がありますね^^
ここについては僕の解説力不足が影響してるかと思います。申し訳ありません。。
過去進行形において重要な要素は下記で、
①時を表す表現
②継続中の動作
の2つです。このうちピンポイントとお伝えしたのは①の部分です。
でこの順番がとても大事です。
●時を表す表現について
最初の例文
We played baseball last Friday. で時を表してるのは
last Friday(先週の金曜日)ですよね。
ここで過去進行形を使う場合、進行形は”継続中の動作”を表すので、
先週の金曜日に他のことを一切することなくずーっと野球をしている必要があります。
それはなかなか考えにくいので、
We played baseball last Friday.として過去の事実を過去形で表すことになります。
上記のように時を表す表現の幅が広いと過去形になることが多く
過去進行形を使う場面はある程度限られてきて、
「電話した時なにしてた?」とか
「家行った時なにしてた?」のように時の部分を絞る必要があるんですよね。
それが「ピンポイント」です。
We were playing baseball when you visited me. は
「(他のことも色々してたけどあなたが家に来たというピンポイントのときは)野球してたよ!」
となるわけです。
整理すると、
①〇時や電話が鳴った時という過去のある時点において(ピンポイント)
↓
②まさにその時は「〇〇してたよ!」(継続中の動作)
と表すのが、過去進行形になります^^
【副詞の位置について】
■質問■
■第三回zoom
・副詞の位置について
頻度を表す副詞の位置について、助動詞が入る文章のときは
助動詞+副詞+動詞とのことでした。
I can usually go~はわかるのですが、
現在形否定文のときのdoも助動詞ですよね?
I usually don’t go ~ではなく、
I don’t usually go~になるのでしょうか?
I really don’t like itとI don’t really like itがnotの位置が違うだけで
「本当に好きじゃない」と「そんなに好きというわけではない」
のように意味がかわる(つまりnotはそれ以降を否定する)のと
同じように、usuallyの場合も両方言えて、意味が異なるのでしょうか?
■解説■
こちら複数の要素があるので分解して解説しますね!
●don’t (doesn’t)の品詞について
こちらご理解いただいている通り、文法上は助動詞に分類されます^^
が、寺子屋の講義では混乱を防ぐためにdon’tは助動詞という伝え方はしてません。
●副詞の位置について
こちらは第3回のアドバンスで詳しく解説をするのですが、
副詞の位置は大きく分けて3つ
①文頭
②文中
③文末
になります。
この内、②の文中については更に細分化できて、
[1]be動詞の直後
[2]一般動詞の直後(ただし目的語がある時は一般動詞の前)
[3]助動詞と動詞の間
[4]be動詞と過去分詞の間
に置かれることが多いです。
ここで多いという言い方をしてるのは、他の品詞のように
文法的に厳しくルールが設けられてる訳ではなく
そうされることが多いもしくは自然とされているからです^^
上記を全て踏まえて今回の例文
※次の解説のために文章補完させてください
I don’t go to school.にusuallyを加えるとなると
②の[3]が適用されますので、
don’t = 助動詞とgo=動詞の間に入って
I don’t usually go to school.
が正しい位置となります!
●notの役割
上記では、 I don’t usually go to school.が正しいと言いましたが、
I usually don’t go to school.も実は正しいです!
これはnotの役割を理解する必要があるのですが、
【notは以下を否定する】
が鉄則になります!
こちらを踏まえた上で2パターン見ていきます。
① I don’t usually go to school.
この場合、not以下はusually go to schoolで、
「いつも学校に行っている」ということを否定するので、
「いつも学校に行っているわけではない」
ここで重要なのはusuallyも否定されているので
「いつもではないよ!」というニュアンスが含まれていることです
②I usually don’t go to school.
この場合、not以下はgo to schoolで、
それがusuallyな頻度で行われてるわけですから、
「私はいつも学校に行かない」
となりご理解いただいている通りニュアンスが異なります^^
日本語訳にしてしまうと平たい意味になり伝わりにくい部もあるかと思いますが、
not 以下を否定するという鉄則を踏まえて読んでいただければと思います。
【一般動詞について】
■質問■
■第一回講義
動画の最後で「一般動詞にイコールの役割はない」と仰っていたのですが、
seem,look,feelなどはイコールの役割を持っている感覚でいました(つまりSVC文型になる)。
例えばYou look sleepy.はYouがなにかを見ているのではなく、
Youが(=)sleepyな状態である。や、 I am happy.はI feel happy.でも言い表せる感覚。
この感覚は持たない方がよいでしょうか?
■解説■
素晴らしい切り口のご質問ありがとうございます^^
この解説は僕の感覚も多分に含まれてましてそのことを
踏まえた上で読んでいただけると幸いです。
●第2文型をとる動詞
こちらは第2回アドバンスで扱いますが、
be動詞以外にも第2文型をとる動詞はいくつかあります。
ご提示いただいている look,seem,feelに加えてbecomeなどもそうですよね^^
ただし、これらはbe動詞と若干性質が違う気がしておりまして、、、
※あくまでも個人の見解ではありますが
例えば、
He is a student.
You are 21 years old.
これらは事実としてイコールが成り立ちますよね。
そして先述した通り、
You look sleepy.は第2文型なので、
You = sleepyとなりますが、
これは「眠たそうに”見える”」という話し手の主観が
入っているように感じるんですよね。
つまり、You are 21 years old.のように You = 21 years old
と100%事実として言えるわけでなくて個人の主観や感想が入っているんです。
なので is と lookを完全に同列で並べるのは微妙だなと個人的に思ってます。
一方で、この話をすると
This book is interesting.の interestingも主観や感想だから
This book = interestingは成り立たないんじゃないかということになるんですが、
今回は一旦それは置いておきます笑
上記を踏まえてam/is/areのような完全なイコールを表すbe動詞と
主観が入るlook/seem/feelなどを一緒にしてしまうのは
教える立場としてどうしても抵抗があり、
「一般動詞にイコールの役割はない」とお伝えをしておりました^^
ただし、文法書にはlookなどもイコールを表すと
書かれてることも多いのでその解釈も正しいと思っています!